Araiです。おかげさまで本業の方が峠を越して少し落ち着いたので、このブログでは初となる試乗記を書いてみようかと思います。私は仕事と趣味の両面で、ジャーナリストの方ほどではないもののそれなりに色々な車に乗せていただく機会があります。せっかくなので私自身の備忘録も兼ねつつ、エンジニア&テストドライバー目線でどう感じたか?が皆様の参考になればと考えております。
正直なところ、見て触れて乗っての感じ方に絶対の正解はないと思っています。あくまで私の感じ方ではありますが、個人ブログの利を活かして忖度なく思いのまま正直に書こうと思います。それではよろしくお願いいたします。
※今回は都合上1時間程度の試乗のため大まかなチェックに留まっていますがご容赦ください。
追記:書き始めたら想定より長くなってしまったので、静的チェックと動的チェックで二部に分けようと思います。もしかしたら三部まで伸びるかも分かりませんが…。
車両概要
- 車種:ポルシェ 911 カレラS (992.1)
- 全長×全幅×全高:4519×1852×1300mm
- ホイールベース:2450mm
- トレッド前/後:1589/1557mm
- 車重:1550kg
- 駆動方式:RR
- エンジン形式:水平対向6気筒3.0Lツインターボ
- 最高出力:450PS/6500rpm
- 最高トルク:530Nm/2300~5000rpm
- 変速機:8速DCT (PDK)
- タイヤ:前245/35ZR20 / 後305/30ZR21
- サス形式:前ストラット / 後マルチリンク
- 価格:約1700万~
内外装デザイン:ポルシェらしいスポーティさと価格に見合う高級感
まず外装は一目で誰もがポルシェと認識する、唯一無二の911のデザインです。時代の要請に合わせて高級で洗練された印象を身に着けつつ、確固たるアイデンティティを守り抜いているところが最大のポイントと思います。空力の観点で言えば決してベストなフォルムやディテールではないと推察しますが、商品として顧客にとっての「ポルシェ911」を崩さずに進化していることが911の911たる所以であると感じます。これは外装に限らず内装も走りも同様に徹底されていていて感心しきりです。
内装は試乗車が黒内装であることも相まってシンプルでクリーンなデザインと感じます。奇をてらわずしっかりと革や金属の素材の美しさを活かしている印象で、各パネルに目障りな主張がないためインパネで主役になるメーターやナビパネル、ステアリングが引き立ち非常に良いモノ感があります。個々人の好みはあるかと思いますが、私は全く不満がありません。ポルシェで言うとエントリーモデルのボクスターでも十分に高級感があるのですが、そこから一段と高級感が高まっており価格差を納得させるだけの質の高さを感じます。
ドライビングポジション:スポーツカーらしい機能性
続いてドライビングポジションに関してです。これはポルシェに共通して感じるところですが、シート座面がかなり下まで下がります。国産車では社外のローポジションレールを入れないと下がらないような位置と思います。シート座面を下げるために、モーター分高さが必要になる電動スライドを採用していない、とは友人談。言われてみればボクスターも背もたれは電動でしたがスライドは手動でした。真偽は分かりませんが説得力のある低さです。
ステアリングは他車と共有かは分かりませんが、ボクスターやカイエンなどと同様に大きめの径でやや細めのグリップです。ベンツやBMWが小径で太めのグリップを採用しているのとは対極と感じます。動的チェックの中でも触れますが、あえて大径のステアリングを採用することで超高速域でのスタビリティとコントロール性を狙っているのかなと想像しました (大径の方が手の動きに対してハンドル角の変化がマイルドになるため) 。この辺は元々不安定になりやすいリアエンジンならではの配慮かもしれません。形状としては今風なDシェイプではなく真ん丸です。ここも5連メーターなどと同様に伝統のイメージを踏襲しているのか、はたまた機能的な理由からこの形状にしているのかは定かではありませんが、私はステアリングは真円であるべきと考えているので好ましく思いました。街乗りやカウンターステアの領域も含めたオーバーオールの操舵では必ず持ち替えが発生するので、そのようなシーンでも引っかからず滑らかで安定した操舵を行うには真円の方がやりやすいから、というのがその理由です。
逆に少し気になったのはペダル配置です。決して踏みにくいといったことはないのですが、全体にペダルが車体中央に寄っていてやや踏み間違い防止に不利な配置と思いました。これはホイールベースの数値にも表れています。911は4座の車としてはかなりホイールベースが短く、2座のスープラで2470mm、フェアレディZで2550mmに対し2450mmしかありません。同じく4座で高性能車であるR35GT-Rで2780mm、小型スポーツのGR86ですら2575mmですから如何に短いかお分かりいただけるかと思います (さすがにロードスターの2310mmよりは長い) 。ホイールベース≒車室スペースであり、後部座席を備える以上はホイールベースから後席足元分のスペースを捻出する必要があるのですが、元が2座以下の長さですからその分だけ前席の足元スペースを削ることになります。するとペダルとタイヤが接近するため、干渉を避けるためにペダルが車体内側へオフセットしてしまうという寸法です。これが本国の左ハンドル仕様であればタイヤに追いやられるのはフットレストなので良いのですが、右ハンドルの場合はアクセルペダルが追いやられてしまうのでアクセル、ブレーキの間隔が狭くなったり極端に言うとブレーキが左足に近い位置までズレてしまいます。ちなみに日本車でも車室空間最優先であるミニバンやコンパクトカーも同様の現象が起きがちです。パニック状態で右足を踏んだ先がアクセルなのかブレーキなのか?安全の観点ではこういったことも気にしています。現状の911が危険な車両であるとは思いませんが、ペダルオフセットが改善されればより安全性の高い車両と言えるとは思います。それにしてもここまでホイールベースが短い理由は何でしょうね?走行性能的にも車室空間的にもホイールベースは長い方が有利なので、近年の車では極力ホイールベースを伸ばすのが主流です。個人的推測では911らしいスタイリングを維持するため…というデザイン面の理由が大きい気がしています。
その他、今回はじっくり確認できていませんが、シートもクッション性、サポート性、乗降性とも不満なくよくできていたと思います。また、スイッチ類も今時のタッチパネルに頼らず物理ボタンを操作しやすい位置に集約して配置されており、また数も多過ぎず少な過ぎず、この辺はさすが走りながらも使える機能的なインターフェースになっていると感じました。とはいえモードセレクトはともかく、電子制御OFFボタンまで使いやすい位置にあるのはスポーツカーらしくやる気に満ちていて笑ってしまいました。
今回はここまでにしたいと思います。走り出す前までにもこういったことは考えながら車に接するようにしています。時間がある時はエンジンルーム内やフロア下面、サスペンションなどもじっくり観察しています。最初のうちは何が何だか分かりませんでしたが、最近は少しずつ見た感じと走行中の現象が結び付いてくるようになりました。分かるようになると車はつくづく面白いなと思います。ではまた動的チェックでお会いしましょう。今回もお読みいただきありがとうございました。

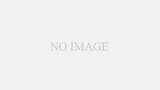

コメント